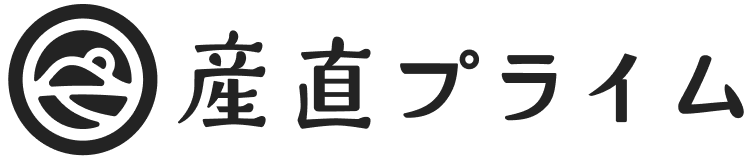めまいと栄養不足の関連性

まずは、めまいと栄養不足の関連性について解説します。
栄養不足が引き起こす体の不調
栄養不足というと、体重減少や肌荒れなどの症状が思い浮かびますが、これらは栄養不足が進行した結果です。初期段階では、疲労感や集中力低下、食欲不振などの症状が現れますが「めまい」もそのひとつです。
栄養が不足して脳への酸素や栄養素の供給が不十分になると、めまいを引き起こすことがあります。思わぬ不調を引き起こさないためにも、バランスの良い食事を心掛けておきましょう。
なぜ栄養不足はめまいを引き起こすのか
栄養不足がめまいを引き起こすメカニズムはいくつかあります。まず、体内のエネルギー源となる栄養素が不足すると、脳への血流が低下し、脳細胞への酸素供給が減少します。これにより、めまいや立ちくらみといった症状が発生します。
特に鉄の不足は身体の酸素輸送能力を低下させ、これがめまいを引き起こします。鉄は血球の成分であるヘモグロビンの材料です。ヘモグロビンは酸素を全身へ運ぶ役割を果たしているため、鉄が不足するとヘモグロビンの合成が妨げられ、酸素の供給が不足します。
また不足するとめまいの原因となるのがビタミンB群です。
ビタミンB群は神経伝達物質の合成に関与します。そのため、不足すると神経伝達物質の働きが悪くなることで起こると考えられている「心因性めまい」を引き起こす可能性があります。
さらにカルシウムの吸収に関わるビタミンDも、脳内の神経伝達物質「セロトニン」の合成に関与していることがわかってきました。
ビタミン不足がめまいの原因となるとは意外ですが、症状が気になる方はビタミンB群やビタミンDが不足していないか、自身の食生活を振り返ってみることも必要かもしれません。
「栄養不足チェック」自身の体を見つめ直す

栄養不足のサインとは何か、自己チェックする方法を紹介します。
まず、体調に異常が見られる場合は栄養不足の可能性があります。具体的には、めまいがする、常に疲れを感じる、肌や髪の状態が悪い、頻繁に風邪を引く、等が挙げられます。
また、食事に関してもチェックする点があります。例えば、1日の食事で野菜や果物、肉や魚など多様な食品群を摂取しているか、また1日3食しっかりと食事を摂っているか等を見直してみましょう。
バランスの悪い食事をとり続けると、めまいなどの様々な不調が起こります。栄養不足は食生活の見直しで改善できます。自身の体調や食事内容をチェックし、必要であれば食生活の見直しを行うことが大切です。
栄養不足の改善!効果的な食事の摂り方

ここからは、栄養不足の改善に効果的な食事の摂り方を見ていきましょう!
栄養バランスのよい食事を心がける
「栄養バランスの良い食事」の基本は「主食」「主菜」「副菜」を揃えることです。主食はご飯やパン、麺など主に炭水化物を含む食品を指します。主菜は肉や魚、卵、大豆製品などたんぱく質をメインに、脂質も摂れるおかずだと考えるとよいでしょう。副菜は野菜類や海藻類、きのこ類など、ビタミンやミネラルが摂れる小鉢のイメージです。
主食と主菜、副菜を組み合わせることで、エネルギー源となる炭水化物や脂質、筋肉や皮膚などの組織をつくるたんぱく質、体の機能を調整するビタミンとミネラルが摂取できます。
特に、めまいの予防にはカルシウムや鉄分などのミネラル、ビタミンB群の摂取が欠かせません。補給したい栄養素を意識しつつも食事はバランスよく、1日3食きちんと摂ることが大切です。
不足しがちな栄養素の補給を意識する
めまい改善に効果的な栄養素の一つが鉄です。鉄が不足すると赤血球中のヘモグロビンの合成がうまくできず、全身に十分な酸素が送れずにめまいや倦怠感を引き起こす可能性があります。主な摂取源は赤身の肉や魚、レバー、小松菜などです。
また、ビタミンCも重要です。ビタミンCは鉄分の吸収を助ける働きを持ち、いちごやキウイフルーツ、柑橘類などの果物に多く含まれています。
さらに、ビタミンB群も不足すると神経系に影響を及ぼし、めまいを引き起こす可能性があります。全粒粉のパンや穀類、肉類に多く含まれています。
これらの栄養素をバランスよく摂取することで、めまいの改善に繋がります。
栄養バランスの良い食事のポイント
「栄養バランスの良い食事」の基本は「主食」「主菜」「副菜」を揃えることです。主食はご飯やパン、麺など主に炭水化物を含む食品を指します。主菜は肉や魚、卵、大豆製品などたんぱく質が摂れるメインのおかずだと考えるとよいでしょう。副菜は野菜類や海藻類、きのこ類など、ビタミンやミネラルが摂れる小鉢のイメージです。
細かな栄養計算をしなくても、主食と主菜、副菜を揃えるだけで、栄養バランスの良い食事に近づけることができます。
めまい予防のために維持したいライフスタイルとは

ここからは、めまいを予防し、毎日を健康に過ごすためのライフスタイルについて紹介します。
適度な運動の意義
適度な運動は、めまいを含む栄養不足による体調不良の予防に重要な役割を果たします。運動は、身体の血流を改善し、栄養素の吸収と分配を助けます。これにより、全身に必要な栄養素が行き渡りやすくなり、めまいを引き起こす可能性のある栄養不足状態を防ぐことができます。
また、適度な運動は自律神経のバランスを整える働きもあります。自律神経は、体内の様々な機能を調節しており、その乱れがめまいを引き起こすこともあるため、適切な運動により自律神経をコントロールすることはめまい予防にもつながります。
ただし、「適度な運動」が重要であり、無理な運動は体調不良を引き起こす可能性もありますので、自身の体調と相談しながら行ってください。
睡眠の質と量の確保
適切な睡眠は身体のリカバリーに必要不可欠です。それは、心と身体の両方である。睡眠不足は体調不良を引き起こし、めまいの原因となる可能性があります。
まず、寝る前の環境を整えることが重要です。ブルーライトが放射されるスマートフォンやパソコン、テレビなどは就寝前はなるべく見ないようにしましょう。寝室は暗く静かに保つことで、質の高い睡眠を支えます。そして、体温調整が睡眠の質に大きく関わることを理解し、適切な寝具を選ぶことも大切です。
次に、睡眠時間も大切です。一般的に睡眠時間には個人差があるものの、1日6〜8時間程度必要であると考えられています。
さらに、毎日同じ時間に寝て起きる習慣をつけると、体内時計が整い、質の良い睡眠が得られます。
睡眠不足は疲労を引き起こし、それがめまいにつながる可能性があります。十分な睡眠をとることで、健康的な生活を維持し、めまいを防ぐことが可能です。
長引くめまいがある場合の対応

長引くめまいがある場合、それは単なる栄養不足だけではなく、重度の病気の可能性もあります。栄養バランスの取れた食事を心がけたり、ライフスタイルを見直したりしてもめまいの症状が改善されない場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
まとめ
今回は、めまいと栄養不足の密接な関連性について解説しました。
めまいは、栄養不足によって引き起こされる症状の一つで、体に不調が起こっているサインです。栄養不足によるめまいを予防・改善するには、鉄分やビタミンCの摂取が重要です。
バランスの良い食生活を心掛け、適度な運動や良質な睡眠の確保など、健全なライフスタイルの維持がめまい改善につながります。
ただし、長引くめまいには専門家の診断が必要な場合もあります。症状に合わせて、食生活の改善や受診などの対策を早めに行いましょう。