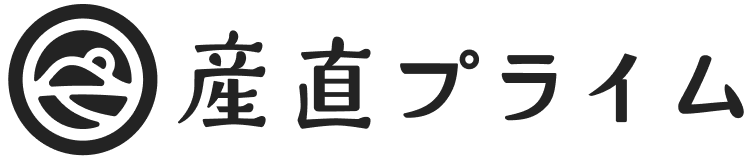目次
びわに含まれる栄養素と効能
まず、びわに含まれている栄養素と効能について解説します。
粘膜や皮膚の健康を維持する「βカロテン」
βカロテンは体内でビタミンAに変換され皮膚や粘膜の健康維持に役立つ成分です。ビタミンAに変換される以外にも、体内で増え過ぎると老化を引き起こす「活性酸素」の働きを抑えたり除去したりする「抗酸化物質」として働きます。
にんじんやトマトなどにも含まれていますが、野菜が苦手だと摂取するハードルが高くなりがちです。しかし、びわなら甘くてさっぱり食べられるので、野菜が食べられない人でもβカロテンが摂取しやすいでしょう。
体内の余分な塩分を体の外に排出してくれる「カリウム」
カリウムには、体内にある余分な塩分を外に排出してくれます。現代人の食生活では塩分の摂り過ぎが問題視されており、塩分を摂りすぎると、むくみの原因になります。びわを積極的に食べることでカリウムを効率よく摂取し、むくみの解消が期待できますよ。
骨粗しょう症を予防する効果のある「βクリプトキサンチン」
βクリプトキサンチンは、βカロテンと同様に体内でビタミンAに変換される成分です。骨密度の減少によって発症する「骨粗しょう症」のリスク軽減が期待できることが報告されているため、骨折を予防したい方は積極的に摂取してみると良いでしょう。βカロテンと同じく、抗酸化作用があります。
活性酸素の働きを抑制してくれる「ポリフェノール」
ポリフェノールは、緑茶や赤ワイン、コーヒーなどに含まれている機能性成分ですが、びわにも含まれています。ポリフェノールには強い抗酸化作用があり、活性酸素による細胞の老化や生活習慣病の予防に役立ちます。いつまでも若々しく、健康的な体を維持したい方におすすめの栄養素です。
便秘改善を助けてくれる「食物繊維」
整腸作用で知られ、便秘解消に役立つ成分が食物繊維です。便秘改善のほか、生活習慣病の予防なども期待できます。食物繊維は、さつまいもやジャガイモなどの芋類に入っているイメージが強いですが、びわにも含まれています。びわは生でそのまま食べられるため、より手軽に食物繊維を摂取したい方におすすめです。
びわは1日何個まで?食べ過ぎるとどうなる?
ここでは、びわを食べすぎた時に起こる症状について解説します。
1日に食べるびわの適量
厚生労働省・農林水産省による「食事バランスガイド」では、1日あたりの果物の摂取量について200g(皮や種を除き)程度を推奨しています。びわ1個だいたい50gで、種などを取り除くと食べられる部分は35gであることを踏まえると、1日の適量は5個程度です。
食べ過ぎると・・・?!
びわには水分や食物繊維が多く含まれているため、食べ過ぎるとお腹が緩くなる可能性があります。
糖質の含有量は100gあたり5.9gと他の果物と比べて特別多いわけではないものの、食べ過ぎればカロリーオーバーとなる可能性もあります。
また熟していない果実や種には「アミグダリン」と呼ばれる有害物質が含まれています。食べることはないとは思いますが、未熟な果実や種は食べないようにしましょう。
びわの健康効果を最大限に活かす!調理のNG
びわの健康効果を最大限に活かす方法について詳しく詳しく解説します。
食べ方①できるだけ生で食べる
びわは、タルトやジャム作りなどお菓子作りにも使われます。しかし、加熱した場合は栄養素が損失してしまう可能性もあるので、できるだけびわに含まれている栄養をそのまま体内に取り込みたいなら、生のまま食べるのがおすすめです。
食べ方②皮も食べる
びわの皮には、βカロテンやカリウムなどの栄養が含まれています。そのため、びわの栄養を摂取したいなら、皮ごと食べるのがおすすめです。ただし、皮にに汚れや農薬がついてしまっているケースもあるので、水でしっかり洗ってから食べるようにしてください。
食べ方③冷蔵庫で冷やしすぎない
冷蔵庫で冷やしすぎると、びわは傷みやすくなります。栄養が豊富に含まれている新鮮な状態で食べるなら、冷蔵庫で保管する場合は、2〜3日以内を目安に消費しましょう。その日中に食べる場合は、2〜3時間ほど冷やしてから食べると良いでしょう。
まとめ|びわはこんな人におすすめの果物!
今回は、びわに含まれる栄養について解説しました。びわは、粘膜や皮膚の健康状態を維持してくれるβカロテンや体内の余分な塩分を体の外に排出してくれるカリウムなど豊富な栄養が含まれています。そのため、健康だけでなく、美容に関心がある方にもおすすめの果物と言えます。記事を参考にびわを美味しく食べてみてください。