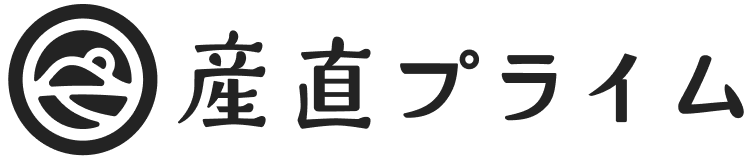あんずに含まれる栄養素と効能
まず、あんずに含まれる栄養素や効能を紹介します。
塩分の摂り過ぎに役立つ「カリウム」
カリウムは、体内にある余分な塩分を体から排出してくれる栄養素です。塩分の摂り過ぎはむくみの原因にもなってしまいます。むくみを解消したい方は、塩分の摂り過ぎに注意すると同時にカリウムも十分摂取しましょう。
皮膚や粘膜の健康を維持する「βカロテン」
βカロテンは体内でビタミンAに変換されて、皮膚や粘膜の健康を維持するのに必要な成分です。また、活性酸素の働きを抑えたり、取り除いてくれる抗酸化作用も期待できるため、老化防止にも役立ちます。食べ物から栄養を摂取して健康維持したい方におすすめの栄養素です。
整腸作用などの効果が期待できる「食物繊維」
食物繊維はヒトの消化酵素で消化できない成分です。消化されずに大腸まで届き、さまざまな効果を発揮します。特に知られているのが整腸作用ですが、脂質や糖も吸着して体の外に排出してくれる役割も果たしています。芋類など良く噛む食べ物に含まれてるケースが多いですが、あんずにも食物繊維は豊富に含まれています。
疲労回復などの効果が期待できる「クエン酸」
クエン酸は、エネルギー産生に関わる成分であるため疲労を回復してくれるのを助けてくれます。また、鉄やマグネシウム、カルシウムなど体に欠かせないミネラルの吸収を高めることが分かっています。睡眠やサプリでも疲労回復できますが、あんずなら様々な栄養素と一緒に摂取できるのが魅力です。
抗酸化作用のある「リコピン」
リコピンは、抗酸化作用があるので、老化や生活習慣病などを防ぐ効果が期待できます。トマトをはじめとする野菜に多く含まれていますが、「野菜は食べられない…」といった人も多いかもしれません。あんずなら甘くて食べやすいので、リコピンを摂取したい人におすすめです。
あんずは1日何個まで?食べ過ぎるとどうなる?
農林水産省「食事バランスガイド」の果物の摂取目安量が1日当たり200g(可食部)程度であること、あんず1個50〜60g程度であることを踏まえると、1日に3〜4個程度が適量であると考えられます。個数だけ見るとたくさん食べられるような印象がありますが、食べすぎると体に悪いので注意が必要です。
食べ過ぎの個数
あんずは、あんずは、1日5個以上食べると食べ過ぎになる可能性があります。あんずは栄養が豊富に含まれていますが、食べすぎてしまうと体に悪影響を及ぼす恐れがあります。下記では食べすぎた時に体に起こる症状について解説します。
食べすぎると・・・?!
虫歯になる
あんずは甘くて美味しいですが、食べすぎると虫歯になる可能性があります。ジャムやシロップに加工した時などは、特に糖分がたくさん含まれるので、食べたら歯磨きを忘れずにしましょう。
カロリーオーバーになる
あんずはカロリーがそこまで高くないので、たくさん食べても問題ないように思われがちですが、たくさん食べすぎるとカロリーオーバーになってしまいます。そのため、食べすぎないように注意が必要です。
下痢になる
あんずには食物繊維が含まれています。適量食べる分には問題ありませんが、食べすぎると下痢や腹痛を引き起こす可能性があるので適量食べるようにしてください。
あんずの健康効果を最大限に活かす!調理のNG
ここでは、あんずの栄養を最大限に生かす食べ方や調理方法について解説します。
食べ方①加熱しすぎない
あんずは加熱してジャムやお菓子作りができる果物です。しかし、加熱しすぎるとあんずに含まれる栄養素が効率よく摂取できない可能性があります。あんずの栄養をしっかり取りたい人は、加熱しないで食べるか、加熱して出てきた煮汁も食べるのがおすすめです。
食べ方②生のまま食べる
あんずの栄養を摂取したいなら、生でそのまま食べる方法が一番おすすめです。酸味が強いのが苦手な場合は、少し追熟させれば、甘くなるので美味しく食べられます。また、そのまま食べるのがおすすめな品種もあるので、生のまま食べなら品種もチェックしてみてください。
食べ方③砂糖や調味料を加えすぎない
あんずは、ジャムやシロップなどに加工する際に砂糖や他の調味料を混ぜて作ります。しかし、調味料が混ざりすぎると栄養が損なわれたり、カロリーオーバーになったりしてしまう可能性があります。そのため、調味料は加えすぎないように注意してください。
まとめ|あんずはこんな人におすすめの果物!
あんずは、皮膚や粘膜の健康維持を助けてくれるβカロテンや便秘解消を助けてくれる食物繊維、体内の塩分を体の外に排出してむくみを解消してくれるカリウムなどが豊富に含まれています。そのため、健康維持や美容に力入れたい人におすすめの果物です。記事を参考に栄養いっぱいのあんずを美味しく食べてみてください。
【参考サイト】