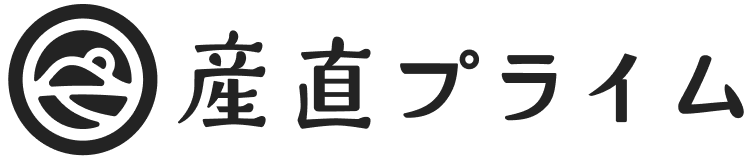枝豆に含まれる栄養素と効能
枝豆に含まれる栄養素と期待できる効能について解説します。
筋肉やホルモンのもととなる「たんぱく質」
枝豆はたんぱく質を多く含んでいます。たんぱく質はエネルギー源となるほか、筋肉や皮膚、毛髪を構成したりホルモンや抗体の成分となったりするなど、体に欠かせない栄養素です。
たんぱく質を多く含む食品といえば肉類や魚類、卵類などを思い浮かべる方も多いでしょう。これら動物性食品と同様に、枝豆のたんぱく質も体内で利用効率の高いたんぱく質です。
糖質の代謝に関わる「ビタミンB1・ビタミンB2」
ビタミンB1は、糖質からエネルギーをつくり出すための補助的な役割を担う栄養素です。ビタミンB1を十分に摂取するとエネルギー産生がスムーズに行われるため、疲労の回復効能が期待できます。
塩分の摂りすぎに役立つ「カリウム」
カリウムは体に不可欠なミネラルの一種です。カリウムには、むくみの要因の一つとなる塩分(ナトリウム)の摂りすぎを調節し、体外へ排出してくれる働きがあります。そのため、減塩に加えカリウムを十分に摂取することでむくみの予防や解消が期待できるでしょう。また塩分の摂りすぎが原因で起こる高血圧の予防・改善にも役立ちます。
アルコール分解を助けてくれる効果のある「メチオニン」
メチオニンは、たんぱく質を構成するアミノ酸のうち、体内で合成できず食品からの摂取が必要となる「必須アミノ酸」の一つです。メチオニンは体内で、アルコールを解毒する肝臓の機能を高める「タウリン」という成分に変換されます。
居酒屋に行くと必ずと言っても良いほど枝豆があるのは、アルコール分解を助けるためと言っても過言ではないのかもしれません。
美容に嬉しい効果のある「イソフラボン」
イソフラボンは、女性ホルモン「エストロゲン」に似た働きをするポリフェノールの一種です。肌のハリやツヤを保ったり、ホルモンバランスの乱れからくる不調を和らげてくれたりする効果も期待できます。加齢による肌や体調の不調を解消したい方にとって、枝豆はおすすめの食べ物であるといえるでしょうす。
枝豆は1日何個まで?食べ過ぎるとどうなる?
枝豆は一日にどのくらい食べて良いのでしょうか。ここでは、一日で食べる枝豆の量の目安と食べすぎてしまった時に発生する症状について紹介します。
食べ過ぎの個数
一日に食べる枝豆の目安は、サヤつきでおよそ140g程度を目安にすると良いでしょう。これは1食当たりの栄養バランスを考慮し主食(ご飯など)、主菜(肉や魚のメインのおかず)を揃えた上で、副菜(野菜や海藻類などのおかず)として摂取する場合の適量です。
たんぱく質をはじめ体に必要な栄養素が含まれている枝豆ですが、それだけではもちろん不十分です。枝豆を含めさまざまな食品を食べるようにしましょう。
食べすぎると・・・?!
枝豆を食べすぎてしまった場合、体にはどういった症状が出るのでしょうか。ここでは、枝豆を食べすぎてしまった時に起こる症状について解説します。
胃腸に負担がかかる
枝豆には食物繊維が豊富です。食物繊維には整腸作用がありますが、摂りすぎは下痢や便秘を引き起こすほか、胃痛の原因になることも。食べすぎにも注意が必要ですが、食べる時にはよく噛むことも意識しましょう。
栄養バランスが崩れたり体重が増加する
🎉最新枝豆ランキング
枝豆ばかり食べると、他の食品から取れるはずの栄養が取れなくなり、1日に摂取すべき栄養バランスが崩れてしまいます。できるだけ多くの種類の野菜を食べて、体にさまざまな栄養を取り入れましょう。また、枝豆のイメージがありますが、食べすぎは禁物です。他の食べ物のカロリーを考慮しながら食べることも忘れないようにしましょう。
枝豆の健康効果を最大限に活かす!調理のNG
枝豆に含まれる栄養を最大限に生かすためには、食べ方や調理方法が大切です。ここでは、枝豆の効果を最大限に生かす食べ方とやってはいけないNG調理方法紹介します。
買ってきたらその日に食べ切る
枝豆は鮮度が落ちやすい食材です。冷蔵や冷凍でも保存はできますが、買ったその日か翌日までに食べるのが一番栄養価が高く美味しく食べられます。栄養素が十分な枝豆を食べたい場合は、食べ切れる量を買うことを心がけましょう。もし、食べきれなかった場合は、早めに冷凍するのがベストです。
冷蔵・冷凍した枝豆はできるだけ早く消費する
枝豆は生の状態で汚れを落とし、冷凍することで1ヶ月ほど保存可能です。それでも美味しさや栄養を保ったまま食べるなら、なるべく早いうちに食べ切るようにしましょう。
できるだけ茹でずに蒸して食べる
枝豆の栄養を逃さず美味しく食べるには、蒸し焼きがおすすめです。コップ半分くらいとなるべく少量の水で蒸すことで、枝豆本来の栄養や食感、風味を逃さず食べられます。
まとめ|枝豆はこんな人におすすめの野菜!
今回は、枝豆に含まれる栄養と効能について紹介しました。枝豆は、下記のような人に特におすすめな野菜です。
- お酒を楽しみたい人
- 美容や健康に気を遣う
- 疲労を長引かせたくない人
調理方法を工夫すると、枝豆の栄養を失わず、より体に取り込めます。記事を参考に栄養がたっぷりの枝豆を美味しく食べてみてください。
【参考サイト】