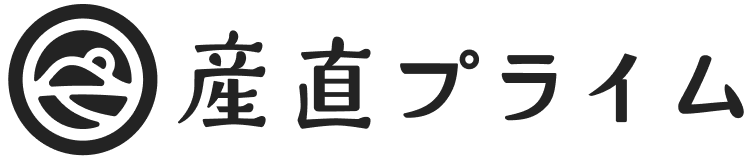5大栄養素とは?
そもそも5大栄養素とは何なのか、ご紹介します。
タンパク質
1つ目はタンパク質です。
タンパク質は筋肉や皮膚、髪の毛などの元になる栄養素です。免疫物質やホルモンをつくる役割もあり、まさに体をつくる栄養素といえます。
糖質
2つ目は炭水化物(糖質)です。
炭水化物(糖質)は体のエネルギーとなる栄養素です。消化吸収の速度が早いのが特徴で、すぐにエネルギーが欲しいときにおすすめです。ご飯やパンなどの主食に多く含まれています。
脂質
3つ目は脂質です。
脂質は1gあたり9kcalほどのエネルギーを生み出せるといわれています。脂質は太ると敬遠されがちですが、少量でもしっかりとエネルギーになるなくてはならない栄養素。神経細胞やホルモンなどをつくる役割があります。
ビタミン
4つ目はビタミンです。
ビタミンは、タンパク質、糖質、脂質の分解、合成をサポートする役割があります。体の調子を整えるために大切な栄養素です。人間の体内ではほぼつくられない栄養素なので、食品から摂取しましょう。
ミネラル
5つ目はミネラルです。
ミネラルは無機質ともいわれ、骨や血液などをつくる役割があります。体の水分や神経の興奮性を調整する働きもあり、ビタミン同様体の調子を整える栄養素といます。
5大栄養素はどんな食品に含まれる?
5大栄養素が含まれている代表的な食品は以下のとおりです。
タンパク質
- 肉
- 魚
- 大豆
炭水化物(糖質)
- 米
- パン
- 根菜(ごぼうなど)
- イモ類(さつまいも、じゃがいもなど)
脂質
- 肉や魚の脂
- マヨネーズ
- バター
ビタミン
- 果物(キウイ、みかんなど)
- 野菜(ブロッコリー、かぼちゃなど)
ミネラル
- 乳製品(牛乳、チーズなど)
- 海藻類(ひじきなど)
栄養バランスの取れた献立
5大栄養素をまんべんなくとれる、栄養バランスのとれた献立が理想的。主食、主菜、副菜、汁物に、牛乳などの乳製品や果物を加えるとばっちりです。3食全てに取り入れるのは難しいかもしれませんが、なるべく栄養素を網羅した献立の例をご紹介します。
【朝食】
目玉焼きと食パン(主食)、野菜サラダ(副菜)、ヨーグルト
【昼食】
ご飯(主食)、生姜焼き(主菜)、ひじきの小鉢(副菜)、野菜のみそ汁(汁物)
【夕食】
ご飯(主食)、サバの塩焼き(主菜)、野菜の煮物(副菜)、豆腐とわかめのみそ汁(汁物)、りんご
栄養素は互いに助け合って働く
栄養素はまんべんなく摂取することで、お互いに助け合って働きます。
タンパク質、炭水化物(糖質)、脂質をそれぞれ単体だけ摂取しても、その役割を十分に発揮することができません。ビタミンやミネラルも、エネルギーそのものにはならないのです。タンパク質が筋肉や髪をつくるときや糖質や脂質がエネルギーに変わるとき、ビタミン、ミネラルが潤滑油としてそのサポートをします。
例えば、糖質がエネルギーに変わるときには、ビタミンB1が必要です。5大栄養素をそれぞれバランスよくとれば、健康で元気な体をつくれるでしょう。
その他の栄養素について
3大栄養素とは?
3大栄養素は、タンパク質、炭水化物(糖質)、脂質のことです。「エネルギー産生栄養素」と呼ばれ、5大栄養素の中でも体を動かすエネルギーになります。
タンパク質は骨や血液などをつくり、炭水化物や脂質は体の力や熱になります。バランスよくとることで、体の調子を整えてくれるでしょう。
6大栄養素とは?
5大栄養素に食物繊維を加えたものを6大栄養素といい、近年その重要性が注目されている栄養素です。
食物繊維には水に溶けない不溶性食物繊維と水に溶ける水溶性食物繊維があります。どちらも小腸で消化吸収されず大腸まで届くので、便秘の解消や腸内環境の改善に効果があるとされています。
まとめ
5大栄養素とは、タンパク質、炭水化物(糖質)、脂質、ビタミン、ミネラルの5つのことを指します。筋肉や血液、神経細胞やホルモンなどをつくる、体づくりには必要不可欠な栄養素です。肉類や魚、野菜や果物などをバランスよくとることで、5大栄養それぞれの役割を十分に発揮できます。元気な体のためにも、いつもの食事に小鉢や牛乳、果物を加えるなど、プラス1品から始めてみてもいいかもしれません。