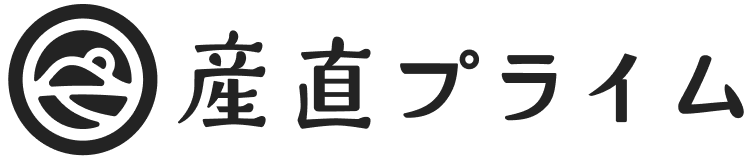はじめに
一般の園芸書を見ると、野菜づくりの1つ目のステップとして、堆肥や肥料を土に混ぜ込む土づくりが紹介されています。有機肥料や化成肥料といった細かい違いはありますが、野菜づくりにおいて肥料は欠かせないものです。
なぜ肥料は必要?
肥料が必要な理由として考えられるのは、①植物自身が作り出すことができないから、②土の中に十分に含まれていないから、の2つです。また、たくさんの肥料を施すことによって早く大きく生長させることができます。
植物は光合成をして空気中の二酸化炭素を取り込み、炭素(C)がつながった糖に変換して体の一部にすることができます。その多くはセルロースと呼ばれる繊維となり体を支えています。
しかし、体を支えるだけでは植物は生きていくことができませんし、植物の体すべてが糖でできているわけではありません。光合成をはじめとする反応に必要な酵素や遺伝情報を持つDNAなどを作るためには、窒素(N)やリン(P)が欠かせません。これらの養分は植物が空気中から作り出すことはできないため、土の中から根を通して吸い上げています。
畑の土の中には、植物が必要としている養分が多少は存在しています。しかし、ただでさえ少ない養分は雑草や土の中の微生物に取られてしまい、野菜は十分に生長することができません。そこで、野菜が生育できるように肥料を与えるとともに、より大きくよりたくさんの実が付くようにしています。

野菜の生育に必要な養分とは
三要素と呼ばれる、野菜の生育に特に必要とされる養分が、窒素(N)、リン(P)、カリ(K)の3つです。この3つは植物が生長するうえで必要とする要求量が多いとともに、土の中で不足しやすい養分のため、必ず肥料として与えることになります。
この3つに、苦土とも呼ばれるマグネシウム(Mg)と石灰とも呼ばれるカルシウム(Ca)を加えて五要素と呼びます。マグネシウムとカルシウムは野菜の生育に必要な養分ですが、通常は土の中にある程度存在しています。
このほかにも10近くの微量要素が必要ですが、日本の場合はその多くが土の中に十分に含まれています。ただし、場所や環境によっては、特定の微量要素が足りなくなり生育が悪くなってしまうため、補う必要がでてきます。
肥料のあげすぎは良くない
「大は小を兼ねるように、肥料を過剰にいれたらいい」とはなりません。土の中で肥料が濃くなると、浸透圧の関係で根が水を吸えなくなってしまいます。
詳しくはこちらの記事で紹介しています。
肥料焼けってなに?肥料の過剰障害 | AGRIs
ついつい良かれと思って肥料をたくさん与えてしまうと逆に株が弱ってしまうことがあります。こうした養分の過剰による生理障害の一つに肥料焼けがあります。この記事では肥料焼けの症状や原因、予防法・対処法を解説します。
https://www.agri-smile.app/articles/fertilizer-excess
NPKはどう使われている?
窒素(N)
窒素はアミノ酸の元であり、主に植物の体内で様々な反応をおこなう酵素タンパク質を作るのにつかわれています。ほかにも、植物が大きく生長するために細胞分裂を繰り返す上で不可欠です。
また、窒素肥料が多すぎる環境では、茎葉を伸ばす栄養生長が促され、花を咲かせて実をつける生殖生長に移行しないため、つるぼけといった生理障害が起こります。こうした性質を踏まえ、窒素は「葉肥(はごえ)」と呼ばれています。
窒素分が不足した場合、作物全体の生育が悪くなり、新しい葉に栄養が優先的に運ばれるため、古い葉から順に色が黄色に変化します。

リン(P)
リンはリン酸の形で吸収、利用されています。リン酸は、細胞膜の主成分として利用されたり、生命のエネルギー源であるATPという物質になったり、遺伝情報を持つDNAやRNAの中に使われています。窒素と同様に植物体全体で利用されています。
エネルギーをたくさん使う開花にはATPが必要であり、リン酸が要求されます。リン酸は花芽分化や果実の肥大を促すともいわれており、「実肥(みごえ)」と呼ばれることもありますが、詳しいメカニズムはわかっていません。
リン酸が不足すると、新しい葉に栄養が運ばれて古い葉が黄化し、すぐに枯れてしまったり、イチゴやナスでは葉が光沢のない濃緑色になったりします。また、トマトなどの果実の成熟が遅延することもあります。

カリ(K)
カリはカリウムの略称で、植物の体の中の物質の移動に関与しています。
植物は葉の裏から蒸散していますが、浸透圧を利用してカリウムがこの蒸散するための孔(あな)をあけています。カリウムの浸透圧は根における水分の吸収にも重要な役割を果たし、根の発育を促すことから「根肥(ねごえ)」と呼ばれます。
また、カリウムは細胞壁を厚くして病害虫への耐性をあげるほか、植物の体の中の物質の移動を促進する効果があり、果実やイモの肥大に影響を及ぼします。
カリウムが不足すると、葉が縁から枯れたり、大きな斑点が生じたり、葉脈を中心に赤紫色になったりといった症状が表れます。
浸透圧
2つの液体が水だけを通す膜を挟んでいる時に、濃度を合わせようとして濃度の低い方から高い方へと水が流れます。この流れようとする力を浸透圧と呼びます。
三要素以外の栄養素
要求量の多いNPK以外にも、植物の生育には多くの栄養素が必要です。
多量要素
マグネシウム(Mg)は光合成をおこなう葉緑素の中心に使われています。苦土石灰の苦土としてまかれ、土の中にある程度存在するため、欠乏することはあまりありませんが、不足すると葉の先が白くなったり、葉の緑色が薄くなったりします。
カルシウム(Ca)は細胞壁や細胞膜の組成にかかわります。土壌の酸度を調整するためにまく苦土石灰に含まれています。Caは植物の体の中で運ばれにくいため、欠乏すると新芽や果実が軟化したり腐ったりといった生理障害が出ます。
硫黄(S)は窒素と同じようにタンパク質の一部に使われています。窒素肥料として使われる硫安(硫酸アンモニウム)など三要素をまく時に一緒に土の中に入ります。欠乏すると窒素欠乏と似たような葉の黄化が見られます。
微量要素
不足すると生理障害が起きますが、量はほとんど必要ありません。ホウ素(B)、マンガン(Mn)、鉄(Fe)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、モリブデン(Mo)、塩素(Cl)、ニッケル(Ni)がほぼすべての植物に共通して必要な微量要素です。
微量要素は土壌がアルカリ性に傾くと欠乏症になることが多くなります。土壌酸度に関してはこちらの記事をご覧ください。
土のpHに注意しよう!土壌酸度のイロハ | AGRIs
園芸書には「土壌のpHは6.0から6.5にしましょう」とよく書かれていますが、そもそもpHは何を表しているのでしょうか。野菜ごとに異なる土壌酸度を好むメカニズムを科学的に解説します。また、土壌酸度を調整するための方法を紹介します。
https://www.agri-smile.app/articles/soil-ph
おわりに
今回は肥料の成分について科学的に解説しました。肥料の効果を理解して、上手に野菜づくりをおこなっていきましょう!
本サイトの有料会員にご登録いただくと、300以上のプロ農家さんの栽培動画が見放題です。ぜひこの機会にご登録してみてはいかがでしょうか。