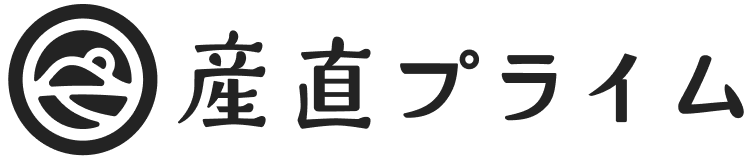料理やお菓子づくりには味のアクセントとなるレモンが欠かせません。またレモンの酸っぱさに、健康に良いイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、レモンに含まれる栄養素とその働きや効果的な食べ方などについて解説します。レモンを食べすぎることによる影響などについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
レモンに含まれる栄養素と効能
強い酸味を持つレモンには、ビタミンCが含まれていることをご存じの方も多いでしょう。
しかし、レモンにはビタミンCのほかにもさまざまな成分が含まれています。
ここではレモンに含まれる栄養素や成分をご紹介します。
コラーゲンをつくる「ビタミンC」
皮膚や軟骨などを構成するたんぱく質「コラーゲン」をつくるのに不可欠なのがビタミンCです。
ビタミンCが欠乏してコラーゲン合成ができなくなると、血管がもろくなり出血しやすくなったり、肌のハリや弾力が失われたりします。
また、体内に増えすぎると老化を引き起こす「活性酸素」の働きを抑えたり取り除いたりする抗酸化物質としても働いています。
その他、ビタミンCは鉄の吸収を高めるなど体内でさまざまな働きを担っているため、多く含む果物や野菜などを積極的に摂取しましょう。
| 状態など | ビタミンC | |
|---|---|---|
| レモン | 全果/生 | 100mg |
| レモン | 果汁/生 | 50mg |
| バナナ | 生 | 16mg |
| りんご | 皮なし/生 | 4mg |
| キウイフルーツ | 緑肉種/生 | 71mg |
| うんしゅうみかん | 生 | 32mg |
| いちご | 生 | 62mg |
整腸作用などの効果が期待できる「食物繊維」
食物繊維は食べ物に含まれる栄養素のうち、ヒトの消化酵素で消化されないまま大腸に届き、体に良い影響をもたらす成分です。
食物繊維は水に溶ける「水溶性食物繊維」と溶けない「不溶性食物繊維」に分類されますが、レモンをはじめとする果物類は比較的2つの食物繊維がバランス良く含まれています。
不溶性食物繊維の主な効果は便通を整える作用。
便のカサが増えることで腸が刺激され、腸の働きが活発化するため、便秘の改善が期待できます。
一方、腸内細菌のうちの「善玉菌」を増やし、腸内環境を良くする作用のあるのが水溶性食物繊維です。
また、血糖値の急上昇を抑えたり血液中のコレステロール値を低下させたりするなど、生活習慣病の予防も期待できます。
| 状態など | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | |
|---|---|---|---|
| レモン | 全果/生 | 2.0g | 2.9g |
| レモン | 果汁/生 | 微量 | 0g |
| バナナ | 生 | 0.1g | 1.0g |
| りんご | 皮なし/生 | 0.4g | 1.0g |
| キウイフルーツ | 緑肉種/生 | 0.6g | 2.0g |
| うんしゅうみかん | 生 | 0.5g | 0.5g |
| いちご | 生 | 0.5g | 0.9g |
ポリフェノールの一種「β−クリプトキサンチン」
みかんの色素に含まれるポリフェノールとして知られているのがβ−クリプトキサンチンです。
抗酸化物質として老化防止に作用するほか、体内でビタミンAに変換される「プロビタミンA」でもあります。
みかんには及ばないものの、レモンにもβ−クリプトキサンチンが含まれています。
| 状態など | β−クリプトキサンチン | |
|---|---|---|
| レモン | 全果/生 | 37μg |
| レモン | 果汁/生 | 13μg |
| バナナ | 生 | 0μg |
| りんご | 皮なし/生 | 7μg |
| キウイフルーツ | 緑肉種/生 | 0μg |
| うんしゅうみかん | 生 | 1,700μg |
| いちご | 生 | 1μg |
疲労回復などの効果が期待できる「クエン酸」
レモンの酸味のもととなっているのがクエン酸です。
クエン酸は体内のエネルギー産生に関わっている成分であるため、疲労回復への効果が期待できるといわれています。
また鉄やマグネシウム、カルシウムなど体に欠かせないミネラルの吸収を高めることが分かっています。
| 状態など | クエン酸 | |
|---|---|---|
| レモン | 全果/生 | 3.0g |
| レモン | 果汁/生 | 6.5g |
| バナナ | 生 | 1.3g |
| りんご | 皮なし/生 | 0g |
| キウイフルーツ | 緑肉種/生 | 1.0g |
| うんしゅうみかん | 生 | - |
| いちご | 生 | 0.7g |
爽やかな香りのもととなる精油成分「リモネン」
レモンをはじめ柑橘類の皮に含まれる成分がリモネンです。
レモンの爽やかな香りはこのリモネンによるものであり、この香りに癒やされるという方も多いかもしれませんね。
最近の研究によると、リモネンには発がん抑制効果などが報告されています。
しかし動物実験の段階でありヒトに対するデータはまだ不十分であることから、今後更なる研究が必要であるとされています。
レモンは1日何個まで?どこからが食べ過ぎ?
さまざまな栄養成分が含まれるレモンですが、1日当たりの摂取量としてはどのくらいが適量なのでしょうか。
食べすぎた場合の影響なども踏まえてみていきましょう。
食べ過ぎの個数
酸味が強いレモンは、一般的な果物のようにたくさん食べすぎることはあまりないかもしれません。
参考までに、農林水産省「食事バランスガイド」の果物の摂取目安量が1日当たり200g(可食部)程度であることを踏まえると、中くらいのサイズのレモンであれば概ね2個程度であると言えます。
レモンを食べすぎると・・・?!
レモンを食べすぎると吐き気や下痢などが生じることがあります。
これはビタミンCを過剰に摂取したことによって起こる症状ですが、通常の食生活を送る健康な方がビタミンCの過剰摂取となる可能性はあまりありません。
通常の食べ方であれば食べすぎることはないため、あまり心配することはないでしょう。
レモンの健康効果を最大限に活かす!調理のNG
せっかくならレモンに含まれる栄養を最大限に取り入れたいものですよね。どのような食べ方がより効率的なのでしょうか。
食べ方①生のまま食べる
レモンに豊富なビタミンCは水溶性および熱に弱い性質があります。
そのためビタミンCを効率良く取り入れるには、生のまま食べるのがおすすめです。
ちなみにクエン酸は熱に強く、加熱しても失われません。
食べ方②果肉も食べる
果汁のみを料理に使うことも多いレモンですが、果肉も食べることで食物繊維が摂取できます。
レモンには不溶性食物繊維と水溶性食物繊維が比較的バランス良く含まれているため、さまざまな健康効果が期待できるでしょう。
酸味が強くそのままでは食べにくい果物なので、料理やケーキ作りに活用すると良さそうですね。
食べ方③鉄やカルシウムの多い食品と一緒に摂る
レモンに含まれるビタミンCは、鉄やカルシウムなどの吸収を高める作用があります。
鉄もカルシウムも、日本人にとっては不足しがちな栄養素です。
これらの栄養素を多く含む食品を摂取することに加え、レモンでビタミンCを補給してみてくださいね。
まとめ|レモンはこんな人におすすめの果物!
レモンにはビタミンCや食物繊維、β−クリプトキサンチンなどが含まれており、以下のような方におすすめの果物であると言えるでしょう。
- 若々しい体を保ちたい方
- 生活習慣病対策を講じたい方
- 便秘がちな方
- 貧血気味の方
- 骨粗しょう症が気になる方
レモンを丸ごと取り入れることで、健康づくりに役立ててくださいね。
【参考サイト】