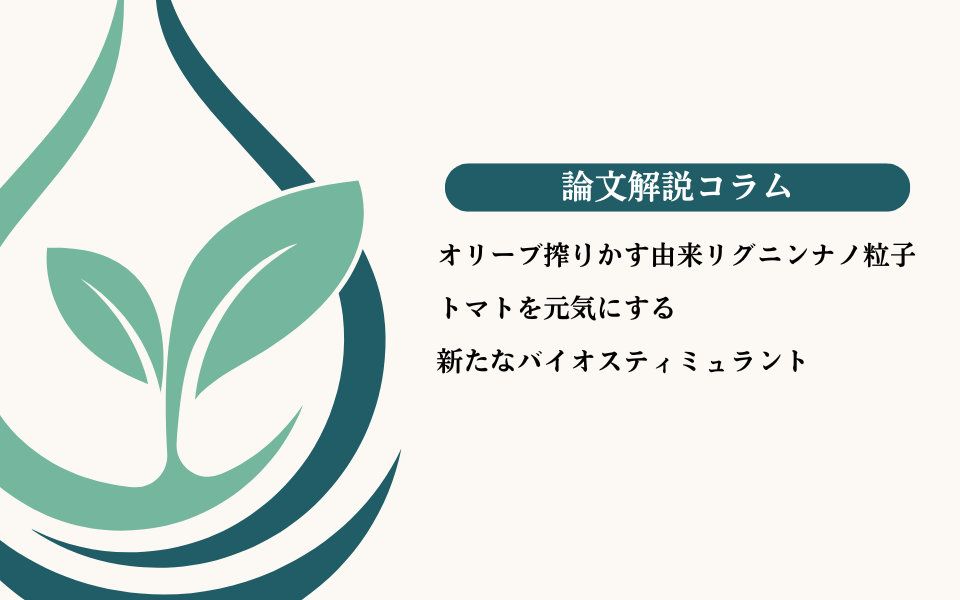葉に大きな穴があく
アオムシ
モンシロチョウの幼虫です。春と秋に発生します。幼虫が小さいうちは小さな穴が空くだけですが、瞬く間に幼虫は成長し、葉脈を残して全部食べてしまいます。

対処法
寒冷紗や不織布をべたがけしたりトンネルにすることで成虫の産卵を防ぎます。幼虫は小さいながらも目視できるので、葉をよく見て一匹ずつ捕殺することができます。大きくなると薬剤も効かなくなるので早めに行動しましょう。
ヨトウムシ
ヨトウガとハスモンヨトウの2種類の幼虫で、茶色や緑色のイモムシです。ヨトウガが春と秋に、ハスモンヨトウが夏から秋にかけて発生します。同時に数百の卵が産みつけられるので、葉裏から集団で穴をあけていきます。幼虫は大きくなると葉脈を残して葉を全部食べてしまいます。

対処法
成虫の産卵を防ぐために、べたがけやトンネルで守ることが一番の予防です。また、日頃から葉の裏をチェックし、卵が産みつけられていたり食害にあっている場合は、その葉ごと処分してしまうのが有効です。「夜盗虫」の名のとおり、成長すると夜行性になり昼間は土中に隠れてしまうため、小さいうちに捕殺または薬剤で対処しましょう。
カブラハバチ
体長が1cmを超える黒いイモムシです。春から秋にかけて多く見られ、夏場は比較的少ないです。葉に大きな穴を複数あけるように食害し、その周りにはフンが点在していることもあります。つつくと丸まって落ちる特性があります。

対処法
防虫ネットをかぶせて、成虫が卵を産みに来るのを防ぐことが先決です。食害が発生した場合でも、幼虫は目視可能なので捕殺することができ、きちんと捕殺すれば新しく出てくる葉はきれいに大きく育って収穫できるでしょう。薬剤散布でも対処することができます。
ナメクジ
春から冬前にかけて発生します。這った跡にねばねばとした粘液がついています。ナメクジに新芽を食べられることで、生長が止まる場合があるので注意が必要です。
対処法
近くのブロックやプランターの下に隠れていることが多いので、見つけた場合は捕殺しましょう。
ヤサイゾウムシ
1cmほどのイモムシのような緑白色の幼虫です。冬や春先に発生します。成虫も幼虫も葉を食害し、葉にたくさんの穴が空きます。薬剤に非常に弱く、他の害虫対策で薬剤を散布していればほとんど発生しませんが、無農薬栽培ではしばしば見られます。

対処法
見つけ次第捕殺します。ハウスで無農薬栽培をする場合にはC字溝トラップも有効です。C字溝トラップは、幼虫の足には吸盤がないため、つるつるした溝に落ちると登ってこられないことを利用したものです。
葉に小さな穴があく
コナガ
ガの幼虫で、体長が5mm~10mmほどの小さなイモムシです。春から冬前にかけて長く発生します。葉の裏から葉の表皮だけ残して食べていくので、食害された部分は白くなった後、穴が空くといった症状が見られます。

対処法
寒冷紗や不織布、防虫ネットで成虫の産卵を防ぎます。被害が見られたら、葉をよく見て一匹ずつ捕殺しましょう。薬剤を利用して対処することもできます。
キスジノミハムシ
体長が3mmほどの甲虫の仲間です。春から秋にかけて広く発生します。成虫は葉に小さな穴をあけるように食べ、幼虫は土の中で根を蝕みます。

対処法
アブラナ科を好む害虫なので、アブラナ科の連作を避けたり、作前に薬剤で土の消毒をしておくことも有効です。発生した場合には薬剤で対処します。
コナダニ
ホウレンソウケナガコナダニという種類で、体長が1mmよりも小さい白い虫です。暑い時期は少ないですが、一年通して発生します。葉に小さい突起や穴ができます。普段は土の中の有機物や菌糸を食べていますが、大発生すると野菜も食べてしまいます。

対処法
発生してしまった場合には薬剤で防除します。未熟な肥料を入れるのを控えることで発生を予防することができます。毎年発生してしまうようであれば、作前に土を消毒しましょう。
【JA監修】今秋リリース予定のAGRIs by JAでは、JA営農指導員さんによる栽培現場のノウハウを徹底的にご紹介します。今ならLINE友だち追加でお得なクーポンをゲット!さらに、プロの栽培技術動画も先行配信いたします。
この機会にぜひお申し込みください!
本気でつくるひとの、そばに|AGRIs by JA
【JA監修】栽培現場のノウハウが学べる新しい農耕プラットフォームです。JA営農指導員さんによる栽培技術動画が見放題。今ならLINE友達追加でお得なクーポンをゲット!(2021年10月1日リリース予定)
https://lp.agri-smile.app/
葉に白い点・模様がつく
ハモグリバエ
ナモグリバエやマメハモグリバエといった種類がいます。4月や8~9月に多く見られます。体長3mm以下の小さなウジで、葉の中で生息します。葉の中を食べながら進んでいくので、食害を受けた葉には白いペンで書いたような跡がつきます。
対処法
葉を挟むようにして潰すことができます。また、食べられた葉を取り除けば、他の葉へ広がることはありません。
アザミウマ
1mmほどの虫で幼虫は白っぽく、成虫は褐色です。春から秋にかけて見られ、夏に多く発生します。葉から汁を吸うので、白い斑点ができたり、葉がちぢれたりします。また、吸い口からウイルスを媒介し、株そのものに病害が発生することもあります。
対処法
成虫が産卵しに来るのを防ぐために、防虫ネットをかけておきましょう。また、アザミウマが発生しやすいネギ、トマト、ナスなどの野菜とは距離をおいて栽培した方がよいでしょう。発生してしまった場合には、薬剤を散布し対処しますが、土の中に隠れていたり薬剤耐性を持ったりしていて効果が薄いこともあるので、予防が特に重要です。
ナガメ
体長1cm以下の黒とオレンジ色の模様をしたカメムシの仲間です。春によく出現します。汁を吸われるとその部分に白い跡がつきます。大量発生すると葉がしおれたりしますが、株全体を枯らすことはほとんどありません。

対処法
防虫ネットをかけ飛来するのを予防しましょう。また、発生した場合は捕殺しましょう。
株が弱る
アブラムシ
体長が1mm~2mmほどの小さな虫です。一年を通して発生します。葉から汁を吸うため、虫食いの穴は空きませんが、葉全体が萎縮するような症状があらわれます。短期間で急速に増殖することがあるので、発生状況をこまめに確認しましょう。また、モザイク病を媒介するため、きちんと予防することが重要です。

対処法
飛来を防ぐために防虫ネットをかけましょう。アブラムシが通れないくらい目の細かいものが良いでしょう。アブラムシを捕殺する際にはテープや歯ブラシなどが便利ですが、アブラムシは小さく数が多いため捕りきるのは難しいです。広がってしまった場合には葉ごと処分するか、薬剤を散布しましょう。
ハダニ
よく見られるのは、ハクサイダニという種類で、体長が1mmほどの黒い胴体に赤い足の生えた虫です。冬に発生します。芯の部分から汁を吸い、葉が白っぽくしわしわになり、最終的に株全体が枯れます。
対処法
捕殺も予防も難しいため、発生してしまった場合には薬剤を綿密に散布して対処します。
おわりに
ここまで害虫ごとの防除方法を紹介してきました。まずは害虫が飛来しないように、防虫ネットをかけて成虫が飛んでくるのを防ぐことができれば、大発生することはありません。防虫ネットのはり方を参考にしつつ対策をしてください。
害虫が発生してしまい薬剤を使う場合には、害虫の種類を正しく見極めることが重要です。本ページの農薬データベース(対象農作物にコマツナ、適用病害虫に害虫名を入力してください)も活用しつつ、適切な防除を行ってください。