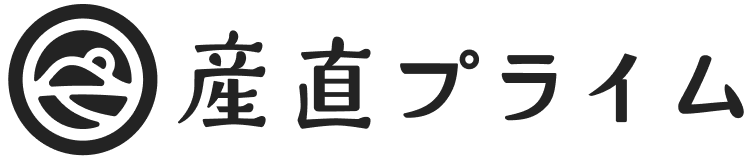日本の桃の生産量は?
日本には、桃を盛んに栽培している地域が多数あり、毎年夏になると各産地から美味しい桃が続々と出荷されます。収穫量は年によってバラつきがあるものの、2020年のデータによると全国で9万8900トンもの桃が収穫されています。
私たちが旬の桃を存分に味わえるのは、桃を大切に育ててくれている生産者の、たしかな技術とこだわりのおかげです◎桃の産地では、より美味しい桃を安定して収穫できるよう、品種改良や栽培方法の改善など様々な試みが行われています。
桃の名産地はどこ?

桃の名産地といわれる地域は全国に多数存在しますが、中でも生産量で上位を占めるのは、以下の5県です。
- 山梨県
- 福島県
- 長野県
- 山形県
- 和歌山県
この5つの産地だけで、国産桃のおよそ80%が生産されています。ここでは、各産地の桃の生産量や栽培の特長について紹介します。
山梨県
桃の生産量1位の山梨県は、日本一日照時間が長い県で、雨も少なく美味しい桃が育つ環境が整っています。栽培面積も日本一で、広大な桃園の景色は「桃源郷」と呼ばれています。そんな山梨県では、桃栽培に適した環境と広大な栽培面積を生かし、29種以上もの品種が栽培されています。収穫量は34,600トンで、全国シェアは約32%です。
福島県
福島県は「日本一の桃好き県」としても有名で、年間の桃の消費量は国内でダントツです。そんな福島県の桃は、明治時代から桑折町や伊達市を中心に広まったとされています。古くから剪定や摘蕾など、冬季から手間をかけて管理し、枝全体にまんべんなく日光が当たるよう工夫するなど、伝統的な栽培技術が受け継がれています。収穫量は約24,300トンで、山梨県に次いで全国2位を誇ります。
長野県
長野県は昼夜の気温差が大きい特有の気候が強みで、糖度が高く良質な桃の産地として有名です。県内でも主要産地である川中島町は、信濃川の南部に位置し、水はけが良い土壌に恵まれています。この地域で誕生した「川中島白桃」は、大玉で濃厚な甘さが魅力の人気品種で、県を代表する特産品です。収穫量は約10,600トンで全国3位となっています。
山形県
山形県は夏でも涼しく桃栽培に適した気候が強みで、他の産地より遅めの8月上旬から10月上旬頃にかけて桃の収穫が行われています。特に山形県さがえ西村山地域は周囲を高い山々に囲まれた盆地で、梅雨でも降雨が少なく昼夜の寒暖差にも恵まれています。そのため山形県の桃は時間をかけてじっくりと生育され、旬を過ぎても大ぶりで甘いのが特徴です。収穫量は約8,800トンで、全国4位となっています。
和歌山県
和歌山県は桃の産地としては気温が高めで、山形県と反対に他の産地より早く桃の収穫が開始されます。和歌山県の桃は収穫時期が7月下旬から10月上旬までと長く、季節ごとに色んな品種を楽しめるのが特徴です。また、袋がけをしない無袋栽培が主流で、見た目よりも味を重視した栽培方法が採用されています。収穫量は約5,730トンで、全国5位となっています。
🍑最新ももランキング
桃の人気品種は?
ここからは、桃の人気品種を紹介します。自分へのご褒美に、大切な人への贈り物にもぴったりな産地自慢の桃たちを、ぜひチェックしてくださいね◎
こちらの記事では、桃の品種についてより詳しく紹介しています。品種ごとの特徴や旬の時期について知りたい人は、ぜひご覧ください!
夢みずき
夢みずきは山梨県果樹試験場が開発したオリジナル品種で、山梨県のみで栽培・出荷されています。生産地が限られているうえ、7月上旬から7月下旬にかけてのわずか1ヶ月ほどしか出回らず、非常に希少な桃として扱われています。
糖度は12〜14.9度と高く、酸味や渋みは控えめで、しっかりとした甘さを感じられます。果汁をたっぷりと含み、ジューシーな食感が際立っています。大玉で見栄えも良いため、贈答品としても人気です。
購入はこちらから
夢みずき【山梨オリジナルの桃品種】
JAフルーツ山梨イチオシの桃を産地直送でお届け!夢みずきは、早生のオリジナル品種として県が開発し、山梨県だけで生産されています。品種名は夢のようにみずみずしい食味の特徴に由来します。夢みずきは「白鳳」系の大玉で糖度は高く、食味も優れていている桃です。ぜひご賞味ください!
夢みずき【山梨オリジナルの桃品種】¥4860〜
送料無料
商品を購入する>
あかつき
「あかつき」は「白桃」と「白鳳」を交配して生まれた品種で、日本一生産量の多い桃です。全国で最も多く栽培されているのは福島県で、国内のあかつきの栽培面積の約半分以上を占めています。特に、福島県桑折町産のあかつきは「献上桃」として皇室に献上されるなど、特に高い評価を受けています。
果実は250~300gほどのふっくらとした扁円形で、日持ちが良く、カリッとした歯ごたえを楽しめることから、硬い桃の代表格とされています。甘みと酸味のバランスがよく、桃らしい爽やかな味わいを楽しめます。あかつきの旬は7月下旬から8月中旬にかけてで、地域によっては8月末から9月上旬頃まで流通しています。
購入はこちらから
【特秀品】あかつき桃 - 福島ももの王道
JAふくしま未来イチオシの桃を産地直送でお届け!あかつきは福島県を中心に、日本で最も多く生産されている桃です。しっかりとした歯ごたえとジューシーさが人気の品種。食欲が落ちてしまいがちな、夏のデザートにぴったりです。ぜひご賞味ください!
【特秀品】あかつき桃 - 福島ももの王道¥5600〜
送料無料
商品を購入する>
川中島白桃
川中島白桃は、長野県長野市川中島町で誕生した品種です。現在は、山梨県、山形県、長野県、福島県など全国的に広く栽培されています。大玉の果実と良好な食味から「桃の王様」と呼ばれ、晩生品種を代表する桃として人気を集めています。
果肉が硬めでパリッとした食感が特徴で、一般的な桃よりも果汁はやや少なめですが、滑らかな舌触りとしっかりとした甘さを楽しめます。旬の時期は産地によって多少前後しますが、早い地域では8月上旬から収穫が始まり、9月いっぱいまで出回ることもあります。
購入はこちらから
【秀品】川中島白桃
JAさがえ西村山イチオシの桃を産地直送でお届け!川中島白桃は、硬い桃の代表品種。大玉でカリッとした歯応えと口いっぱいに広がる強い甘みが特徴です。色づきも良く、贈答品としても最適です。ぜひご賞味ください!
【秀品】川中島白桃¥5750〜
送料無料
商品を購入する>
白鳳
白鳳は、そのジューシーさととろける食感、バランスの良い甘みで人気の高い桃の代表品種です。主な産地は山梨県、和歌山県、岡山県で、この3県で全国の収穫量の約80%を占めています。特に、山梨県は全国シェアの約50%を占めており、最大の産地です。
白鳳は果汁が非常に豊富で、皮を剥いただけで滴り落ちるほどジューシーな味わいです。果肉は柔らかく、とろけるような口当たりが特徴で、強い甘みと控えめな酸味のバランスに優れています。白鳳は桃の中でも比較的早い時期に出回り、最も美味しいピークは7月半ば前後とされています。
購入はこちらから
山梨のもも 1.5kg【旬の品種をお届け】
JAフルーツ山梨イチオシの桃を産地直送でお届け!ももの生産量 日本一の山梨県。特に高品質なももの産地として知られるのが峡東地域(甲州市・山梨市・笛吹市)で、世界農業遺産に認定された伝統的な産地です。白鳳は山梨県の桃の中でも人気の高い自慢の逸品です。ぜひご賞味ください!
山梨のもも 1.5kg【旬の品種をお届け】¥3510〜
送料無料
商品を購入する>
🍑最新ももランキング
【豆知識】美味しい桃が育つ条件とは?

介した5つの産地にも、それぞれ栽培の特長は違えど、自然条件はある程度共通しています。
これから桃栽培をはじめたい人や、美味しい桃が育つ条件についてより詳しく知りたい人はぜひ参考にしてください◎
十分な日照時間
美味しい桃が育つ条件としてまず第一に大切なのが、太陽の光をたっぷり浴びること。桃は太陽の光を浴びれば浴びるほど、甘くなるといわれています。
また桃の甘さは雨によって拡散してしまうため、年間の雨量と日照時間は、美味しい桃を育てるうえで非常に重要なポイントです。
水はけの良い土壌
桃の木は過度な湿気を嫌い、土壌がいつまでも湿って泥のような状態になっていると、実りが悪くなるといわれています。
そのため桃を育てる土壌は水はけが良く、乾きやすいことが条件となります。緩やかな傾斜や盆地などでは、比較的よく桃が育つとされています。
昼夜の気温差が大きい気候
一見あまり関係なさそうですが、実は昼夜の気温差にも美味しい桃が育つ条件が含まれています。
桃は日中にたっぷりと太陽の光を浴びて、夜に気温がぐっと下がることで活発に栄養を吸収し、甘みが増すといわれています。そのため昼夜の気温差が大きい地域ほど、糖度の高い桃が育ちやすいとされているんです。
まとめ
今回は、桃の産地や品種について詳しく紹介しました。日本一の桃の産地は山梨県で、全国シェアの約32%を占めます。他にも、福島県、長野県、山形県、和歌山県など、日本には美味しい桃を育てている産地がたくさんあります。
各産地には、それぞれ主力となる品種が存在し、地域を代表する特産品にもなっています。夏を彩る代表的な果物である桃。産地ごとの特色や品種にも注目しながら、その魅力を存分に楽しんでくださいね◎
桃を食べてJAさがえ西村山の挑戦を応援しよう!

さくらんぼや桃、りんごなどのフルーツをはじめ、日本で有数の「米どころ」としても知られる山形県さがえ西村山地区。豊かで寒暖差のある自然環境と生産者のたしかな技術によって、「さくらんぼの王様」といわれる佐藤錦など、四季折々の美味しい食べ物を全国にお届けしています。
そんなさがえ西村山地区に拠点を置き、山形県の中央エリアを管轄するJAさがえ西村山では、2023年より「環境にやさしい栽培技術」と「省力化に資する先端技術等」を取り入れた「グリーンな栽培体系」を目指し、新たな取り組みをスタートしています。
気候変動問題が世界中のイシューとなる中で、全国の生産者にはカーボンニュートラルの実現に向けて化学肥料の低減が求められています。(みどりの食糧システム戦略)
とはいえ、化学肥料を減らすと、収入減少の怖さがあり、生産者にとって大きな負担を強いる可能性があります。そこでJAさがえ西村山では、バイオスティミュラントという新しい農業資材に着目し、生産者の負担を軽減する、新しい栽培方法の開発に挑戦しています。
【引用元】バイオスティミュラント 活用による 脱炭素地域づくり協議会

特に、栽培過程で生じる「ゴミ」である食品残渣からバイオスティミュラントを生産することで、「食品から食品」を生む環境負荷の低い栽培を実現し、気候変動に負けない、持続可能な産地を目指しています。
現在、さがえ西村山地区では「さくらんぼ」「桃」「りんご」「米」「なす」の5品目でこの取り組みを実施しているそうです。ぜひ、気候変動問題に果敢に取り組む産地の商品を購入して応援していきましょう!