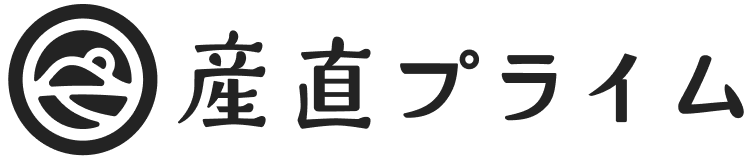日本一の干し柿の産地は?生産量推移
日本で一番干し柿が作られている場所は、長野県です。長野県では4126.5tもの干し柿を生産しています。日本で作っている干し柿の多くは長野県で作られています。中でも一番生産されている「市田柿」は、小さいサイズで食べやすく、きめ細やかな 粉がついているのが特徴です。もちっとした食感と上品な甘さは、甘いものを食べたいけどできるだけヘルシーなものが良いという方におすすめです。
美味しい干し柿ができる条件とは?
美味しい干し柿ができるには下記の3つのポイントがあります。
- 太陽の光をたっぷり浴びる
- 直接てでさわらない
- 雨が降ったら室内に移動させる
それぞれ詳しく解説します。
条件①太陽の光をたっぷり浴びる
干し柿は、皮を剥いた後、天日干しして作られます。太陽の光をいっぱいに浴びさせて干すことで、柿に含まれる渋み成分のタンニンを抜いて、甘く美味しくなります。そのため、できるだけ太陽の光が当たる場所に置いて作るのがポイントです。
干し柿を作る生産者は、ハウスや室内で干し柿を作っている場合もありますが、ひもで吊るして干したり、太陽の光が当たるように並べて干しているケースもあります。自宅で干し柿を作る場合は、ベランダや庭で干して太陽の光が当たるようにすると良いでしょう。食べ頃の干し柿はカラスや虫が寄ってくるので事前に網をかけておくと安心です。
条件②直接てでさわらない
干し柿を作る時は、直接手で触らないようにするのがポイントです。もし、触ってしまうと、干し柿に雑菌がついてしまう可能性があります。ビニール手袋をはめて清潔な状態で作りましょう。
条件③雨が降ったら室内に移動させる
干し柿は、大きいサイズで1週間、小さいサイズだと2週間ほど干します。ほとんどの場合、外で干すケースが多いため、雨が降っていたり、じめっとした日には部屋に避難させましょう。
雨が降っていなくても湿度が高いとカビが生えたり、干し柿が黒っぽい見た目になってしまいます。そのため、湿度が高い日は室内に避難させて、できるだけ風通しの良い場所につるしておくのがポイントです。
あの地域がなぜ?干し柿の名産地の秘密に迫る!
ここでは、干し柿が一番作られている都道府県と特徴について解説します。
【1位】長野県の干し柿生産の特長
長野県は、日本で一番干し柿の生産量が多い都道府県です。中でも長野県下伊那郡高森町で生産されている「市田柿(いちだかき)」が最も人気が高いです。市田柿(いちだがき)は、ハウスや室内で湿気・カビが生えないように気をつけながら丁寧に作られています。見た目は、きめ細かい白い粉がついており、食べやすい小さいサイズなのが特徴です。実は弾力があり、上品な甘さなので、初めて干し柿食べる人におすすめの品種です。旬は12月ごろなので、美味しい市田柿(いちだがき)を食べたい人は、このタイミングを狙って購入してみてください。
【2位】福島県の干し柿生産の特長
福島県では、伊達市や国見町を中心に、古い歴史と伝統的な技術を用いてつくられている「あんぽ柿」が多く生産されています。「あんぽ柿」は水分が残っており、実は柔らかく、とろっとしたような食感が特徴の干し柿です。他の干し柿に比べて強い甘さがあるので、干し柿の固い食感や甘さが控えめなものが苦手で、甘みが強いものを食べたい方におすすめです。
【3位】和歌山県の干し柿生産の特長
和歌山県は柿の生産量が多く、干し柿も盛んに生産されています。中でも、和歌山県では、日本全国の中で最もポピュラーな平核無(ひらたねなし)の渋柿を使った干し柿を作っています。平核無(ひらたねなし)は、四角のような見た目でサイズが大きく、タネがないのが特徴です。あんぽ柿にすると、とろっとした食感が楽しめて、ころ柿を作るとぎゅっとした固い食感が楽しめます。
まとめ
今回は美味しい干し柿ができるポイントや産地について解説しました。干し柿は、日本全国で作られていますが、都道府県によって有名な品種があります。また、「あんぽ柿」「ころ柿」など、味や食感が異なるものもあります。美味しい干し柿を見つけたいなら産地や生産方法もチェックしてから購入するのがおすすめです。記事を参考に美味しい干し柿を見つけてみてください。