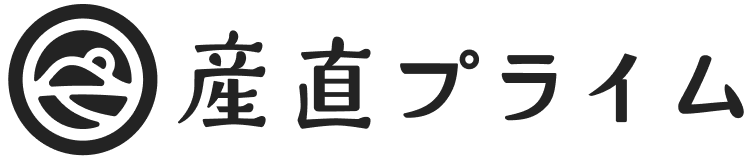洋梨はすぐに食べるべき?食べ頃はいつ?

洋梨はもぎたてを食べても美味しくない果物です。実は洋梨の甘くてとろけるような味わいは、収穫後に「追熟」という過程を経ることで生まれるのです。
ここでは、洋梨の完熟について見ていきましょう。
追熟とは
収穫後の未熟な果実を、一定期間置いて完熟させることを追熟といいます。追熟を必要とする果物は、洋梨のほかバナナやキウイフルーツ、マンゴーなどです。
洋梨は、品種によっても異なりますが室温(15〜20度)に2日〜2週間ほど置くことで完熟し、食べ頃になります。
追熟のポイントと注意点
追熟を早めたい場合は室温に置くのがおすすめですが、高温多湿の場所は避けましょう。特に夏場などで室温が30度近くなるような場合は、追熟に失敗したり傷んでしまったりすることがあります。暑い時期に洋梨の追熟を行う場合は、冷房の効いた部屋に保管しましょう。
逆に追熟を遅らせて日持ちさせたい場合は、洋梨を乾燥させないように新聞紙やペーパータオルなどに包み、冷蔵庫の野菜室などに保存します。
洋梨の食べ頃サインは?

洋梨が完熟したら、傷んでしまわないうちに早めに食べたいもの。ここでは洋梨の食べ頃のサインについてご紹介します。美味しいタイミングで洋梨を味わうためには、ぜひチェックしておいてくださいね!
ポイント①皮の色が変化する
まずは洋梨の皮の色に注目しましょう。品種によっても異なりますが多くの洋梨は、未熟の時は緑色、食べ頃になると黄色っぽくなってきます。軸側に緑色が残っていても、お尻側が黄色くなっていれば食べ頃である可能性は高いでしょう。
なお、ラフランスのように熟してもあまり黄色くならない品種もあるため、この後紹介するポイントと合わせて確認するのがおすすめです。
ポイント②軸の周りが柔らかくシワのあるもの
皮の色がちょうど良さそうなものは、軸の周りをそっと触ってみてください。少し柔らかさを感じるようであれば、今が食べ頃です。触れてみなくても、この部分の皮にシワが見られたり軸が枯れてきたりしていれば、食べ頃の洋梨であるといえます。
ポイント③甘い香りがする
洋梨の特徴のひとつである独特の甘い香りがしてきたら、食べ頃を迎えた証拠です。洋梨特有の香りは、完熟しないと出てきません。
皮の色や軸周りの硬さ、シワに加え、香りも考慮することで洋梨の食べ頃を確実に捉えることができるでしょう。
食べ頃を過ぎた洋梨はどうしたらいい?

食べ頃を迎えた洋梨は冷蔵保存で3〜4日ほど持ちますが、傷んでしまわないうちになるべく早めに食べ切りましょう。ここでは食べ頃を過ぎた洋梨の特徴や、おすすめの食べ方をご紹介します。
食べ頃を過ぎてしまった洋梨
軸や軸周りの皮にシワがより、周辺の果肉も柔らかさが感じられる頃が洋梨の食べ頃。しかしそんな時期を過ぎてしまうと、全体が柔らかくなり、最終的には果肉がドロドロとして溶けたような状態になってしまいます。
果肉が柔らかくなり過ぎたと感じても、酸っぱい匂いや嫌な臭いがしていないなら食べても問題ない可能性はありますが、カビが生えている場合は食べるのを避けるべきです。
食べ頃を逃してしまわないように、洋梨を買い置きした場合は状態をこまめにチェックしておきましょう。
食べ頃を過ぎた洋梨のアレンジレシピ
食べ頃が過ぎたとはいえ、まだ食べられそうな洋梨は、コンポートなどにアレンジして消費すると良いでしょう。ジャムにするのもおすすめです。
コンポートやジャムは、ヨーグルトに添えたりやスイーツ作りに使ったりといろいろな用途で活躍しますよ。特にジャムは適切な方法で保存すれば、長期保存も可能です。
まとめ

追熟させることで甘く美味しくなる洋梨。手に入れた洋梨がまだ完熟ではない場合は、食べ頃になるまで追熟しましょう。洋梨の食べ頃を見極めるのは難しいといわれていますが、保管場所などに気を配ったりこまめにチェックしたりして、食べ頃のサインを見逃さないようにしてくださいね。